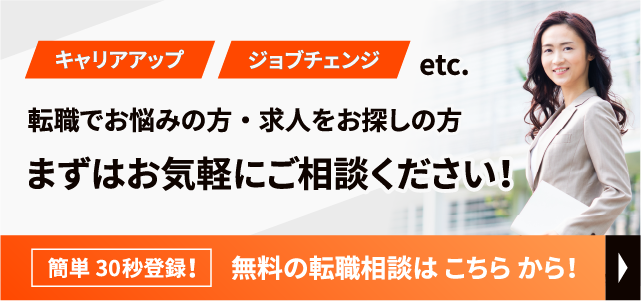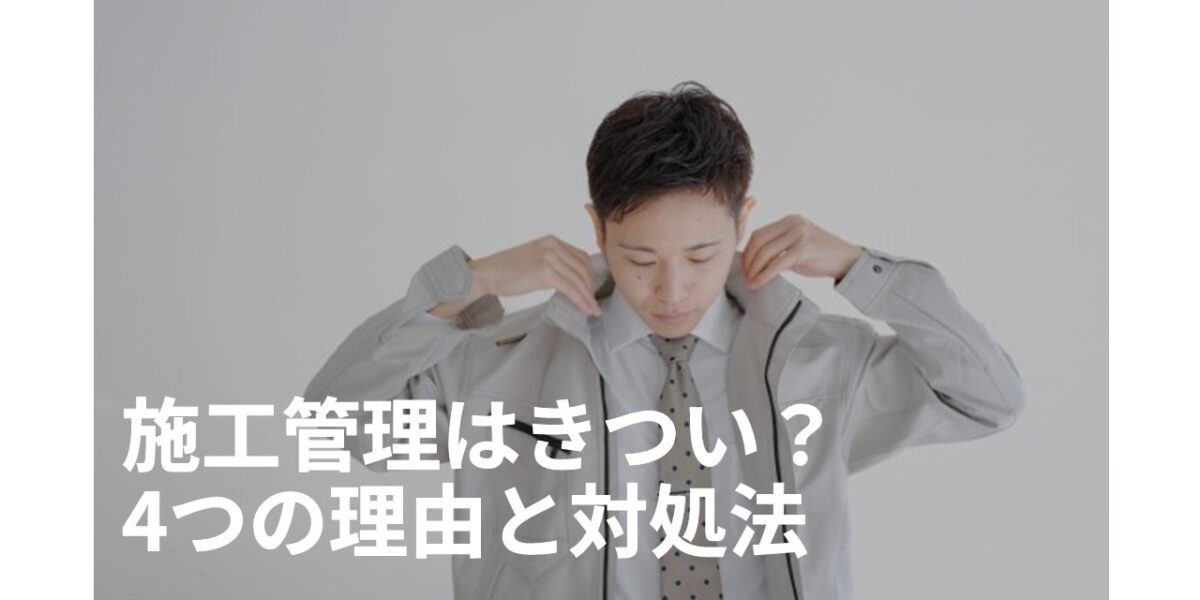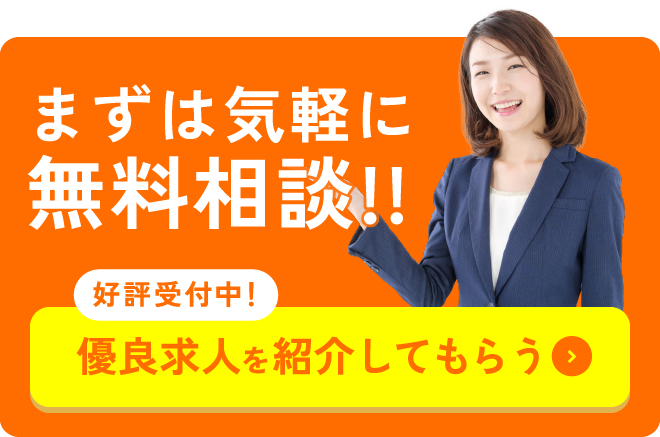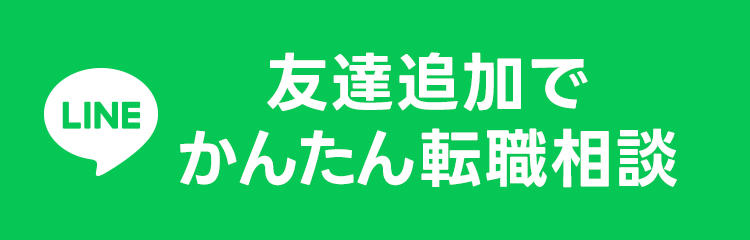【2025年】電気工事施工管理技士とは?1級・2級の仕事内容や年収を解説
施工管理転職豆知識
2025.09.05
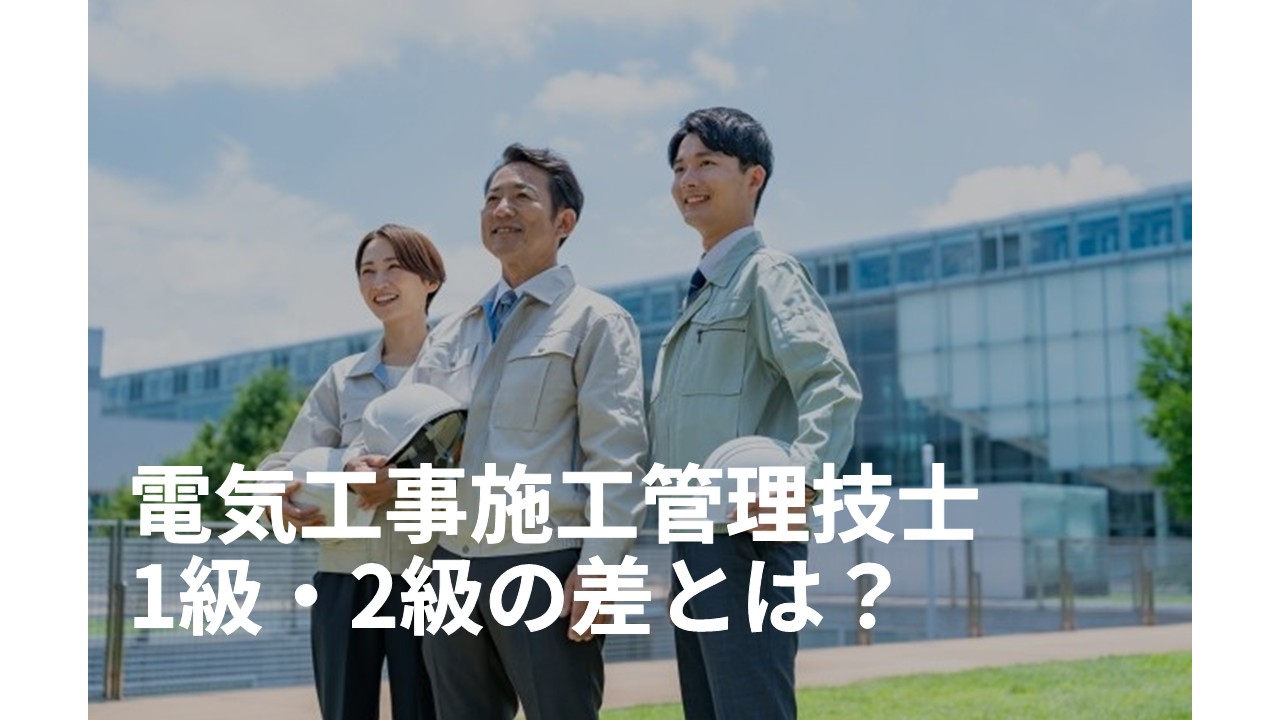
電気工事施工管理技士とは、電気工事の現場を管理・監督する専門家であり、建設業界で高い需要を誇る国家資格です。建物の新築や増築、改修に伴う電気設備の工事において、計画から完成までを一貫して管理する重要な役割を担います。
この資格には1級と2級があり、それぞれ担当できる工事の規模や範囲が異なります。
本記事では、電気工事施工管理技士がどのような仕事をするのか、その年収はどのくらいなのか、そして資格取得のメリットや試験制度、さらには2025年の最新試験情報まで、電気工事施工管理技士という資格の全体像を網羅的に解説します。
電気工事施工管理技士というキャリアに興味がある方にとって、有益な情報を提供できるよう努めます。
電気工事のスペシャリスト!電気工事施工管理技士の役割
電気工事施工管理技士は、建設現場における電気工事の施工管理を専門とする国家資格者です。
電気設備工事が計画通りに進むよう、多岐にわたる管理業務を担当します。具体的には、電気工事の施工計画の作成や、工事現場での工程管理、品質管理、原価管理、安全管理などが挙げられます。
これらの仕事は、電気工事の品質と安全を確保するために不可欠です。
また、電気工事の需要は高く、建設業界において重要なポジションを占めています。
電気工事施工管理技士の具体的な仕事内容
電気工事施工管理技士の仕事内容は多岐にわたり、電気工事の最初から最後まで、責任者として携わります。
主な仕事は、施工計画の作成、工程管理、安全管理、品質管理、原価管理の4大管理に加え、発注者や役所との連絡調整、資材の発注、下請け業者の選定も含まれます。
これらの仕事を通じて、電気工事の品質と安全を確保し、プロジェクトを成功に導くことが電気工事施工管理技士の重要な役割です。
建設現場のスケジュールを管理する「工程管理」
電気工事施工管理技士の仕事の一つである工程管理は、電気工事が計画通りに進行するようスケジュールを管理する業務です。
具体的には、工事全体のスケジュール作成や進捗状況の把握、遅延が発生した場合の原因究明と対策立案などを行います。
これにより、工事の円滑な進行と工期の遵守を目指し、プロジェクト全体の成功に貢献します。
また、他の工種との連携も密に行い、全体工期に影響が出ないよう調整することも重要な役割です。
事故を防ぎ安全な現場を維持する「安全管理」
電気工事施工管理技士の仕事において、安全管理は最も重要な業務の一つです。工事現場での事故や災害を未然に防ぎ、作業員全員が安全に働ける環境を確保することが求められます。
具体的な業務としては、安全対策の計画立案、危険箇所の特定と改善、安全衛生教育の実施、作業員の健康状態の管理などが挙げられます。
これらの取り組みを通じて、安全な工事現場を維持し、作業員の命と健康を守ることが電気工事施工管理技士の責務です。
建物の品質を確保するための「品質管理」
電気工事施工管理技士の仕事における品質管理は、完成する電気設備が設計図書や仕様書通りの性能や品質を満たしているかを確認管理する重要な業務です。
使用する材料の検査、施工方法の確認、完成後の検査などを通じて、建物の電気設備が安全かつ適切に機能することを保証します。
この品質管理を徹底することで、利用者の安全性はもちろんのこと、建物全体の信頼性を高めることにも繋がります。
予算内で工事を収める「原価管理」
電気工事施工管理技士の仕事における原価管理は、電気工事にかかる費用を予算内に収めるための重要な業務です。
具体的には、材料費や人件費、外注費などのコストを正確に把握し、無駄をなくすための計画を立て、実行します。
予算超過のリスクを低減し、利益を確保するためには、常にコスト意識を持ち、効率的な資源配分を考える必要があります。
この原価管理の能力は、プロジェクトを経済的に成功させるために不可欠です。
1級と2級で何が違う?担当できる工事の規模を比較
電気工事施工管理技士の資格には1級と2級があり、基本的な仕事内容は共通していますが、担当できる工事の規模や配置される役職に違いがあります。
1級は大規模な工事現場で監理技術者として、2級は中小規模の工事で主任技術者として活躍できる点が主な相違点です。
大規模な工事現場で監理技術者になれる1級
1級電気工事施工管理技士は、特定建設業が請け負う大規模な電気工事において、監理技術者として配置されることができます。監理技術者は、令和7年2月1日施行の改正建設業法により、請負金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)の工事現場に配置が義務付けられている役職であり、工事全体の技術的な管理・指導を行います。
また、1級電気工事施工管理技士は、営業所に設置が義務付けられている専任技術者や、主任技術者にもなることが可能です。大規模な建設現場でキャリアアップを目指す方にとって、1級電気工事施工管理技士の資格は非常に価値が高いといえるでしょう。
中小規模の工事で主任技術者を務める2級
2級電気工事施工管理技士は、一般建設業が請け負う中小規模の電気工事現場において、主任技術者として配置されることができます。
主任技術者は、工事の施工計画から工程、品質、安全、原価の各管理を担い、現場の技術的な責任者として重要な役割を果たします。
2級電気工事施工管理技士の資格は、担当できる工事規模に制限があるものの、電気工事の幅広い業務に携わることができ、キャリアの第一歩として非常に有効です。
電気工事施工管理技士の資格を取得する3つのメリット
電気工事施工管理技士の資格を取得することは、個人のキャリアアップだけでなく、企業にとっても多くのメリットをもたらします。
この資格を持つことで、転職やキャリアアップに有利になったり、企業からの評価が向上し年収アップに繋がったり、特定の重要な役職に就けるようになったりします。
転職やキャリアアップで有利になる
電気工事施工管理技士の資格は、建設業界における転職やキャリアアップにおいて非常に有利に働きます。
建設業界全体で施工管理技士の需要が高まっているため、資格取得者は即戦力として高く評価され、自身のスキルをアピールしやすくなります。
特に1級資格を保有していれば、大規模な現場での監理技術者としての活躍が期待され、より良い条件の求人に応募できる可能性が広がります。
企業からの評価が上がり年収アップにつながる
電気工事施工管理技士の資格は、企業からの評価を高め、年収アップに直結する大きなメリットがあります。
電気工事施工管理技士の平均年収は、国税庁が公表する日本人の平均年収を上回る傾向にあり、約496万円とされています。
1級電気工事施工管理技士の場合、500万円から700万円程度とさらに高い年収が期待できるでしょう。
企業は資格を持つ人材を確保することで、受注できる工事の幅が広がり、売上向上に繋がるため、資格取得者に対して資格手当や昇進といった形で給与を優遇する傾向があります。
営業所に必須の「専任技術者」になれる
電気工事施工管理技士の資格を取得することで、建設業法で定められた「専任技術者」になることができます。
専任技術者は、建設業の許可を受けるために営業所に必ず配置しなければならない重要なポジションです。
この専任技術者になれることは、企業にとって資格保有者がいること自体が事業運営上のメリットとなるため、資格の価値を高める要因の一つとなります。
結果として、資格保有者は企業から重宝され、安定したキャリアを築くことが期待できます。
気になる年収は?給与水準と収入アップの方法
電気工事施工管理技士の年収は、日本人の平均年収と比較して高い水準にあります。
平均年収は約496万円ですが、雇用形態や地域、経験年数、企業の規模、担当する工事の条件などによって給与水準は大きく変動します。
収入アップのためには、1級電気工事施工管理技士の取得や関連資格の取得、またはより良い条件の企業への転職などが有効な方法となります。
【2025年最新】電気工事施工管理技術検定の試験概要
電気工事施工管理技術検定は、電気工事の施工管理に携わる技術者の能力を評価するための国家試験です。
2025年も例年通り実施される予定で、1級と2級で試験日程や受験資格が異なります。
令和7年度の試験日や申込期間、試験内容、そして新制度に対応した受験資格など、詳細を確認しておくことが重要です。
試験は第一次検定と第二次検定の2段階で行われ、それぞれ異なる形式と内容が出題されます。
試験の難易度と近年の合格率
電気工事施工管理技士の試験難易度は、1級・2級ともに中程度から高程度とされています。
近年の合格率を見ると、1級の第一次検定では30%台から40%台、第二次検定では50%前後で推移しており、2級の第一次検定は45%〜55%程度、第二次検定は40%〜60%程度となっています。
決して低い合格率ではありませんが、試験範囲が広いため、計画的な学習が重要です。
2025年度の試験日程と申込期間
令和7年(2025年)の電気工事施工管理技術検定の試験日程は以下の通りです。
1級の第一次検定は7月13日(日)、第二次検定は10月19日(日)に実施されます。
2級の第一次検定(前期)は6月8日(日)、後期(第一次検定・第二次検定)は11月9日(日)です。
申込期間は1級の第一次検定が2月14日(金)から2月28日(金)、2級の前期第一次検定は2月7日(金)から2月28日(金)となっています。
願書の購入期間も設けられているため、早めに準備を進め、余裕を持って申し込みを行いましょう。
新制度に対応した受験資格の詳細
電気工事施工管理技術検定の受験資格は、令和6年度から新制度に移行し、これまでよりも受験しやすい形となりました。
1級の第一次検定は、試験実施年度に満19歳以上であれば学歴や実務経験は問われません。
2級の第一次検定は、満17歳以上であれば受験可能です。
ただし、第二次検定を受験するためには、第一次検定合格後に所定の実務経験が必要となります。
なお、令和10年度までは旧制度の実務経験で第二次検定を受験することも可能です。
自身の学歴や実務経験に応じて、最適な受験資格を確認することが重要です。
第一次検定と第二次検定の試験内容
電気工事施工管理技術検定は、第一次検定と第二次検定で構成されており、それぞれの試験内容に特徴があります。
第一次検定はマークシート形式で、電気工学、施工管理法、法規など幅広い分野から出題され、受験者の総合的な知識が問われます。合格基準は、全体の得点のうち60%以上であり、かつ施工管理法の分野で50%以上の得点とされています。
一方、第二次検定は記述式問題が中心となり、実際の電気工事に関する応用能力や経験に基づいた知識、語句の理解などが問われます。
特に第二次検定の記述式問題は、過去問を繰り返し解くだけでは対策が難しい側面もあるため、実務経験に基づいた表現力も必要となります。
試験問題の傾向を把握し、それぞれの内容に合わせた対策を立てることが合格への鍵となります。
合格を目指すための効率的な学習方法
電気工事施工管理技士の試験合格を目指すには、効率的な学習方法を確立することが重要です。
独学で進めるか、予備校や通信講座を活用するか、自身の学習スタイルや環境に合わせて選択すると良いでしょう。
試験範囲が広いため、計画的に学習を進めることが大切です。
独学で合格するためのポイント
独学で電気工事施工管理技士の合格を目指す場合、過去問を繰り返し解くことが最も重要なポイントです。
試験問題は過去の出題傾向が強く、同じような問題が形を変えて出題されることが多いため、過去問を完璧に理解することが合格への近道となります。
特に第一次検定は、過去問演習とテキストでの復習を繰り返すことで、知識の定着を図れます。
第二次検定は記述式のため、過去問を解くだけでなく、解答の書き方や文章構成についても対策が必要です。
毎日少しずつでも勉強時間を確保し、計画的に学習を進めることが、独学で合格するための鍵となるでしょう。
予備校や通信講座を活用するメリット
独学での学習が難しいと感じる場合や、より効率的に合格を目指したい場合は、予備校や通信講座の活用も有効な勉強方法です。予備校や通信講座では、試験に出る要点に絞った講義動画や専用のテキストが用意されており、効率的な学習が可能です。
特に、第二次検定の記述式問題は独学では対策が難しいと感じる人も多いため、プロによる添削指導や分かりやすい解説は大きなメリットとなります。また、質問対応などのサポート体制も充実しているため、疑問点を解消しながら安心して学習を進められるでしょう。
まとめ
電気工事施工管理技士は、電気工事の計画から管理までを一貫して行う、建設業界において非常に重要な国家資格です。
この資格を持つことで、転職やキャリアアップに有利に働き、年収アップも期待できます。
特に1級電気工事施工管理技士は、大規模な工事の監理技術者として活躍できるため、キャリアの幅が大きく広がります。
試験は第一次検定と第二次検定に分かれており、それぞれ異なる対策が必要ですが、適切な学習方法と計画を立てることで合格は十分に可能です。
電気工事に関わる仕事に興味がある方や、自身のキャリアをさらに発展させたいと考える方にとって、電気工事施工管理技士の資格取得は、将来を切り開く大きな一歩となるでしょう。