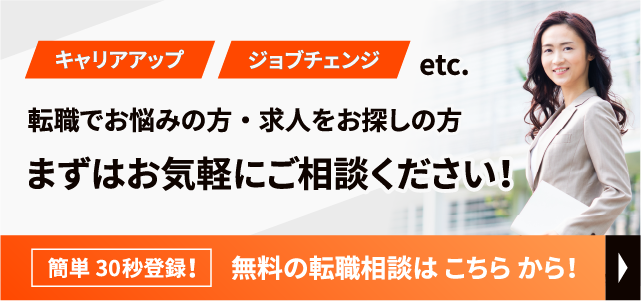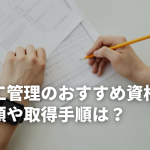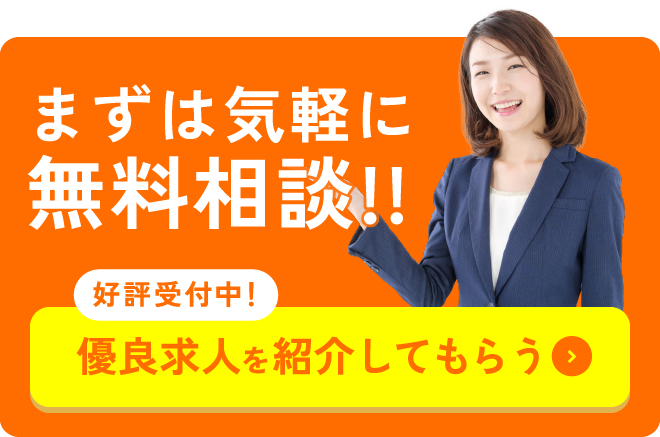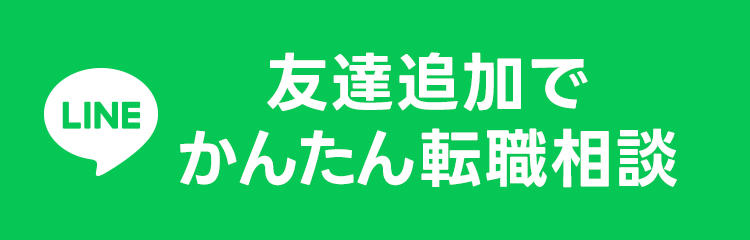設計士と建築士の違いとは?仕事内容・年収・資格の差を解説
CAD・設計職建築士業界あれこれ転職豆知識
2025.09.01

設計や建築の仕事に興味がある方、これから家を建てようと考えている方にとって、「設計士と建築士」という言葉はよく耳にするものの、その具体的な違いが分かりにくいと感じるのではないでしょうか。
この二つの職種は、どちらも建物の設計に携わりますが、資格の有無や業務範囲、さらには年収やキャリアパスにおいて明確な差があります。
本記事では、「設計士と建築士」の違いを徹底的に解説し、それぞれの仕事内容、必要な資格、そして将来のキャリアについて詳しくご紹介します。
「設計士」と「建築士」の根本的な違いは資格の有無
「設計士」と「建築士」の最も大きな違いは、国家資格の有無にあります。
建築士とは、一級建築士、二級建築士、木造建築士などの国家資格を保有している人のことを指し、国や都道府県知事からの認可を受けて取得する専門的な資格です。
一方、「設計士」という資格は存在せず、一般的に設計業務に携わる人の総称として使われます。
そのため、建築士は「設計士」でもありますが、設計士は必ずしも「建築士」ではありません。
建築物の設計・工事監理といった特定の業務は、建築士の国家資格を持つ者のみが行える独占業務とされています。
設計士は資格がなくても名乗れる呼称
設計士の定義は明確に定められておらず、資格がなくても名乗れる呼称です。
設計士は、主に小規模な木造建築物の設計や、建築士の補助業務に携わることが多いです。
具体的には、延べ面積が100平方メートル以下の小規模な建築物の設計や、建築士のアシスタントとして設計の一部を担当したり、事務作業をサポートしたりすることがあります。
このように、設計士の業務は多岐にわたりますが、あくまでも建築士の資格が必要な設計業務には直接携わることができない点に注意が必要です。
しかし、設計士として実務経験を積むことは、将来的に建築士資格の取得を目指す上で貴重な経験となります。
建築士は国家資格を持つ専門家
建築士は、国や都道府県知事から認可を受けて取得する国家資格です。
建築士の資格を取得するためには、専門的な知識が幅広く必要とされ、難易度の高い試験に合格する必要があります。
建築士は、建造物の設計と工事監理を行う技術者であり、これは建築士の独占業務とされています。
建築士の資格は、設計できる建造物の種類や規模に応じて、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類に分かれています。
専門学校などで建築を学び、所定の実務経験を積むことで、これらの資格取得を目指すことができます。
仕事内容はどう違う?設計士と建築士の業務範囲を比較
建築士と設計士は、どちらも建物の設計に携わる仕事ですが、その業務範囲には明確な違いがあります。
建築士は国家資格に基づき、設計と工事監理という独占業務を行うことができます。
一方、設計士は資格を必要としないため、業務範囲が限定され、主に建築士の補助的な役割を担います。
ここでは、それぞれの職種が具体的にどのような内容の仕事を担当するのかを比較し、それぞれの役割について詳しく見ていきましょう。
設計士が担当する主な業務範囲
「設計士」は特定の資格を指すものではなく、建築物の設計業務に携わる人を広く指す呼称です。一方、「建築士」は一級建築士、二級建築士、木造建築士といった国家資格を指します。建築物の設計を行うには、原則としてこれらの建築士資格のいずれかが必要です。
建築士の主な仕事内容は、設計・工事監理業務、お客様からの要望のヒアリング、設計に必要な情報の収集、施工会社との打ち合わせ、設計図書の作成などが挙げられます。
延べ面積が100平方メートル以下の木造建築物の設計については、建築士の資格がなくても可能な場合がありますが、延べ面積が50平方メートルを超える建築物で、その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものは建築士の資格が必要です。
また、建築士の資格を持たない「設計士」も、建築士のアシスタントとして、建設許可や道路の使用許可申請などの行政手続きのサポート、事務作業などを担当することがあります。これらの業務経験は、将来的に建築士の資格取得を目指す上で役立つことがあります。 ハウスメーカーなどで働く場合、お客様の要望を形にするための設計プランニングや、設計図の作成に携わることもあります。
建築士が独占的に行える専門業務
建築士ができることは、建築物の設計と工事監理という法律で定められた独占業務です。
設計は、建物の構造、設備、外観、内装、材料、工事方法などを具体的に決め、工事に必要な設計図や仕様書を作成する業務です。
工事監理は、実際の工事が設計図書通りに進められているかを確認し、必要に応じて指導・監督を行うことです。
これら以外にも、建設許可や道路の使用許可申請などの行政手続き、建築主と施工業者の契約書監修や内容折衝、建築物に関する調査鑑定なども建築士の重要な内容です。
これらの業務は、建物の安全性や機能性を確保するために、専門的な知識と技術が求められます。
建物のデザインを決める「意匠設計」
意匠設計は、建物のデザインと機能性を決定する重要なプロセスです。建築士は、クライアントの要望やイメージを具体的にヒアリングし、それを形にするためのデザイン案を立案します。
間取りや外観のデザイン、使用する材料、内装のコーディネートなど、建物の美しさや使いやすさに直結する要素を設計します。単に見た目のデザインだけでなく、光の取り込み方、風通し、動線なども考慮し、快適で魅力的な空間を作り上げることが求められます。
良いデザインは、建物の価値を高め、住む人や利用する人の満足度を大きく左右する重要な業務です。
安全性に関わる「構造設計」
構造設計は、建物の骨組みや基礎など、安全性と耐久性を確保するための構造を設計する業務です。地震や風などの外部からの力に耐えられる建物であるか、適切な材料が使われているかなどを計算し、構造図を作成します。
物理学や数学の知識を駆使し、建物の構造的な安定性を確保することが求められます。特に、高層ビルや大規模な公共施設など、複雑な構造を持つ建物においては、高度な構造計算と深い知識が不可欠となります。
構造計算一級建築士の資格を持つ建築士は、さらに専門的な構造設計を行うことができます。
快適性を左右する「設備設計」
設備設計は、建物における電気、水道、空調、給排水、情報通信などの機械設備を設計する業務です。
建物の快適性や機能性を左右する重要な要素であり、省エネルギー性や環境への配慮も考慮されます。
例えば、エアコンの配置や換気システムの設計、照明計画、コンセントの位置、配管ルートなど、利用者が快適に過ごせる空間を提供するために、細部にわたる検討が必要です。
設備設計一級建築士は、特に高度な設備設計を専門に行います。
法律を守るための「工事監理」
工事監理は、設計図書通りに工事が進められているかを建築士が確認し、指導・監督する業務です。
建設現場で、使用される材料や工法が適切であるか、建築基準法などの各種法律や条例に適合しているかなどを厳しくチェックします。
設計図と実際の工事にずれがないかを確認し、問題があれば修正指示を出すことも建築士の重要な役割です。
建築士は、発注者の代理人として、工事の品質と安全性を確保し、建物が法律に則って完成するように責任を負います。
建築士資格の種類と設計できる建物の違い
建築士の資格は、設計できる建物の種類や規模によって3つに分類されています。
それぞれ「一級建築士」、「二級建築士」、「木造建築士」と称され、取得難易度や業務範囲が異なります。
これから建築の道を目指す方や、家を建てようと考えている方にとって、それぞれの資格でどのような建物を設計できるのかを理解することは非常に重要です。
ここでは、各建築士資格の具体的な業務範囲について詳しく解説します。
一級建築士:あらゆる建物の設計が可能
一級建築士は、国土交通大臣から免許を受ける国家資格であり、設計できる建物に構造や規模の制限がありません。
学校、病院、劇場、公会堂、集会場、百貨店といった大規模な建物から、一般住宅まで、あらゆる種類の建物を設計することが可能です。
例えば、高さ13m以上または軒の高さが9mを超える建物、鉄筋コンクリート造や鉄骨造で延べ面積が300平方メートルを超える建物などは、一級建築士でなければ設計できません。
そのため、一級建築士は、大規模プロジェクトや多様な建物の設計に携わりたいと考える人にとって、非常に有利な資格と言えるでしょう。
二級建築士:主に戸建て住宅など小規模な建物を設計
二級建築士は、都道府県知事から免許を受ける国家資格であり、主に戸建て住宅などの小規模な建物の設計・工事監理を行います。
設計できる建物には、構造や規模に一定の制限がありますが、2025年4月1日の建築基準法改正により、その範囲が広がります。
改正後は、階数3以下、高さ16m以下の建物が対象となります。
鉄筋コンクリート造や鉄骨造の場合、延べ面積の制限が緩和される見込みです。
木造の建物であれば、延べ面積300平方メートルを超えると構造計算が必要になりますが、階数3以下、高さ16m以下であれば二級建築士が設計できるようになります。
二級建築士の資格は、住宅の設計やリフォームなど、比較的小規模な建物を設計したい方に適した資格と言えるでしょう。
二級建築士は、一般的な家を設計するのに必要な資格となります。
木造建築士:木造建築物の設計に特化した資格
木造建築士も、二級建築士と同様に都道府県知事から免許を受ける国家資格です。
この資格は、その名の通り、木造建築物の設計・工事監理に特化しています。
具体的には、2階建て以下の木造建築物で、延べ面積が100平方メートルを超え300平方メートル以内の建物を設計することが可能です。
木造建築士は、日本の戸建住宅に多い木造建築に特化した知識と技術を持つため、伝統的な木造建築や、小規模な木造リフォームなどに強みを発揮します。
しかし、木造以外の構造や大規模な建物には携わることができないため、より幅広い建物を設計したい場合は、二級建築士や一級建築士の資格取得も視野に入れるとよいでしょう。
年収はどれくらい違う?設計士と建築士の給与事情
建築や設計の仕事を目指す上で、年収は重要な要素の一つです。
設計士と建築士では、資格の有無や業務範囲の違いから、給与事情にも差が生じます。
ここでは、それぞれの職種の平均年収の目安と、資格の有無が年収にどのように影響するのかについて詳しく解説します。
自身のキャリアプランを考える上で、ぜひ参考にしてください。
設計士の年収の目安
設計士の平均年収は、所属する企業の規模や地域、経験年数によって大きく異なりますが、一般的には350万円から500万円程度とされています。大手企業や都市部に勤務する場合は、平均年収が上がる傾向にあります。
設計士は、建築士の補助的な業務や、小規模な木造建築物の設計が主な仕事となるため、建築士と比較すると給料が低い傾向にあります。
ただし、経験を積んでスキルを磨けば、独立して年収アップを目指すことも可能です。設計士としての経験は、将来的に建築士資格を取得する際の重要な実務経験にもなります。
建築士の年収の目安
建築士の年収は、資格の種類や経験年数、勤務先によって大きく変動します。
一級建築士の平均年収は、約600万円から800万円程度と言われています。
特に、大手設計事務所やゼネコン、大手ハウスメーカーに勤務する一級建築士の場合、800万円を超える年収も珍しくありません。
二級建築士の平均年収は、一般的に400万円から600万円程度が目安となります。
経験を積んだり、独立開業したりすることで、さらに高い給料を得る可能性もあります。
建築士は、資格を持つことで業務範囲が広がり、高年収を期待できる職種と言えるでしょう。
資格の有無が年収の差に直結
設計士と建築士の年収には明確な差があり、これは資格の有無が大きく影響しています。
建築士は国家資格を持つ専門家として、法律で定められた独占業務を行うことができるため、その専門性が年収に反映される傾向があります。
特に一級建築士は、あらゆる建物の設計や工事監理ができるため、より大規模なプロジェクトに携わる機会が増え、平均年収も高くなります。
一方、設計士は資格がなくても名乗れる呼称であり、業務範囲に制限があるため、建築士と比較すると年収は低い傾向にあります。
建築業界で高年収を目指すのであれば、建築士資格の取得が重要なステップとなるでしょう。
設計士や建築士として活躍するために必要なスキル
設計士や建築士として活躍するためには、専門的な知識や資格だけでなく、多岐にわたるスキルが求められます。
建物の設計は、単に図面を描くだけの作業ではありません。
クライアントの要望を的確に捉え、安全で快適な空間を創造し、多くの関係者と協力しながらプロジェクトを成功させる必要があります。
ここでは、設計士や建築士として不可欠なスキルについて詳しく解説します。
顧客の要望を形にするデザイン力と発想力
設計士や建築士にとって、顧客の要望を具体的な形にするデザイン力と発想力は不可欠な能力です。
顧客が漠然と抱いているイメージや希望を正確にヒアリングし、それを機能的で美しいデザインに落とし込む必要があります。
単に要望に応えるだけでなく、予算や法規制、敷地の条件などを考慮しながら、より良い提案を行うための柔軟な発想力が求められます。
新しいアイデアを生み出し、それを魅力的にプレゼンテーションする能力も、顧客の信頼を得る上で重要です。
図面を立体的に捉える空間把握能力
設計士や建築士の仕事において、図面を立体的に捉える空間把握能力は非常に重要な知識でありスキルです。
平面の設計図から、完成後の建物の姿や空間の広がり、光の入り方、動線などを頭の中で正確にイメージする力が求められます。
特に、複雑な構造や多層階の建物では、各フロアや部屋の関係性を把握し、全体として矛盾のない設計を行う必要があります。
この能力は、CADなどの設計ツールを使いこなす上で基礎となり、デザインの検討や施工時の問題解決にも役立ちます。
関係者と円滑に仕事を進めるコミュニケーション能力
設計士や建築士の仕事は、顧客だけでなく、施工業者、行政機関、協力会社など、多くの関係者との連携が不可欠です。
そのため、円滑に仕事を進めるためのコミュニケーション能力は非常に重要な能力となります。
顧客の要望を正確に理解し、専門的な内容を分かりやすく説明する力、施工現場での指示出しや問題解決のための交渉力、そして様々な意見を調整し、プロジェクト全体を円滑に進めるための協調性が求められます。
良好な人間関係を築き、チームとして最高の成果を出すために、優れたコミュニケーション能力は欠かせません。
設計士から建築士を目指すキャリアプラン
設計士として実務経験を積んだ後、建築士資格の取得を目指すのは、建築業界でのキャリアアップにおいて一般的なキャリアプランです。
建築士の資格は、業務範囲を広げ、より専門的な仕事に携わるための重要なステップとなります。
ここでは、設計士が建築士を目指す具体的な道のりと、資格取得後の多様なキャリアパスについて解説します。
実務経験を積みながら資格取得を目指すのが一般的
設計士から建築士を目指す場合、実務経験を積みながら資格取得を目指すのが一般的な道のりです。
建築士の受験には学歴や実務経験の要件があり、例えば、建築系の学歴がなくても7年以上の実務経験があれば二級建築士の受験資格が得られます。
実務経験を通じて建築に関する知識やスキルを身につけ、同時に資格取得のための勉強を進めます。
建築士の試験は難易度が高いですが、日々の業務で得られる経験は、試験の理解を深める上で非常に役立ちます。
計画的に学習を進め、着実にステップアップしていくことが重要です。
建築士資格取得後の多様なキャリアパス
建築士資格を取得すると、キャリアパスは大きく広がります。例えば、設計事務所で独立して自身の理想とする建物を追求したり、大手ゼネコンやハウスメーカーで大規模なプロジェクトに携わったりすることができます。また、リフォーム会社や工務店、さらには地方自治体の建築部門で公務員として働くなど、多様な選択肢があります。
一級建築士として5年の実務経験を積めば、さらに上級の構造設計一級建築士や設備設計一級建築士の資格取得も可能となり、より専門性の高い分野で活躍できるようになります。
建築士の資格は、将来の転職やキャリアアップにおいて大きな強みとなるでしょう。
まとめ
設計士と建築士は、どちらも建物の設計に携わる仕事ですが、その最も大きな違いは国家資格の有無にあります。
建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士といった国家資格を持つ専門家であり、設計や工事監理という独占業務を行うことができます。
一方、設計士は資格がなくても名乗れる呼称で、主に小規模な建物の設計や建築士の補助業務を担当します。
仕事内容や年収にもこの資格の有無が大きく影響しており、建築士の方が業務範囲が広く、高収入を期待できる傾向にあります。
建築業界で活躍するためには、デザイン力や空間把握能力、コミュニケーション能力といったスキルも重要です。
設計士として実務経験を積んだ後、建築士資格の取得を目指すことで、キャリアパスは大きく広がり、より専門的で大規模なプロジェクトに携わる道が開けるでしょう。